冬の本屋[書店]情報
通販、書店、どちらでも購入できる!冬の人気書籍のご紹介/ホームメイト
今や絵本や小説などの書籍は、書店だけでなく通販や電子上で購入できるようになり、読書がより身近なものとなっています。そこで今回は、冬にまつわる人気の書籍のご紹介です。寒い冬に暖かい部屋で、じっくりと読書をするのはいかがでしょうか。
親子で読みたい、冬に人気の子ども向け書籍
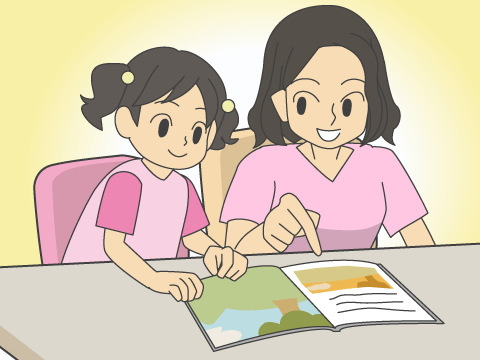
子どもに人気の高い、冬を題材にした書籍は、いずれも子どもだけでなく、大人が読んでも面白いと思えるものばかりです。童心に返ってお子さんと一緒に読書を楽しんでみてはいかがでしょう。その中でおすすめなのは、加古里子(かこさとし)作「だるまちゃんとうさぎちゃん」。絵本作家の加古里子が描く人気シリーズの第3弾で、主人公のだるまちゃんが、うさぎちゃんと色々な冬の遊びを楽しむお話です。ほのぼのとした画風とともに、雪の遊び方、手袋人形の作り方など、懐かしい冬の遊びも紹介されています。雪が降った日に、ぜひお子さまに読み聞かせてあげましょう。
次に紹介する絵本は、新美南吉作「手ぶくろを買いに」。新美南吉による、児童文学の名作です。新美南吉が生涯をかけて追求したテーマは「生存所属を異にするもの同士の魂の流通共鳴」。難しい言葉ですが、「手ぶくろを買いに」では、そのテーマが、キツネと人間という登場キャラクターを通し「異なる生き物同士の魂の交流」として、小さな子にも分かりやすく書かれています。また、美しい日本語で表現されており、読み聞かせに適した絵本です。
最後にご紹介するのは、ウクライナ民話「てぶくろ」。ウクライナに古くから伝わる昔話です。おじいさんが落としてしまった手袋に、次々と集まってくる動物たちを描きます。「次にやってくる動物は誰かな?」とお子さんと推理しながら読んでいくのも楽しいのではないでしょうか。寒い冬に心が温かくなる1冊として人気です。
大人におすすめ、書店で人気の冬の名作書籍
大人向けの冬の名作書籍は、書店だけでなく通販でも人気の高いものばかり。長い冬の夜、じっくり読書をするのもおすすめです。小川未明(おがわびめい/おがわみめい)作「冬の寒い日に読みたい童話」は、冬を題材にした童話10選が収録された書籍。小川未明の作風は、本作にも収められている「赤い蝋燭と人魚」を代表とするように、大人向けと子ども向けを区別しないリアリズムがあります。大人が読んでも深い味わいのある、小川未明の世界に触れてみるのはいかがでしょうか。
次にご紹介するのが、黒木亮作「冬の喝采」。箱根駅伝を題材とした、作者の自伝的小説です。作者は経済小説家として有名ですが、大学時代はマラソンランナーとして活躍していました。そんな彼の出生の秘密や、苦しい競技生活を題材としている人間ドラマを描いた長編小説です。
そして、人気作家東野圭吾が、真冬のスキー場を舞台に描いた恋愛小説「恋のゴンドラ」。全7章で構成されており、章ごとに登場人物それぞれの恋物語が進行していきます。最終章で登場人物全員の物語が完結するのですが、そこに向かって複雑に絡み合う人間模様が楽しめるところも、この作品の醍醐味。最後にはどんでん返しも用意されています。
通販で人気、冬に売れる人気書籍
大人子ども問わず、冬に人気の高い書籍は、年賀状やクリスマスカードが作成できる書籍から、冬の料理本まで様々です。
年末に近くなると数多く販売されるのが、年賀状作成ソフト付きの書籍。付属の作成ソフトを使用して、パソコンで簡単に年賀状が作成できる書籍は、年末になると人気です。カタログのデザインが豊富な点が人気で、大人向けだけでなく、子ども向けにアニメのキャラクターがデザインされたものも多く出版されています。さらに、喪中はがき、寒中見舞いのデザインもできるので、1冊あれば非常に便利です。
また、クリスマスパーティー用の料理本や、バレンタインデーのチョコレートの作り方を特集した書籍も、冬になると売れ行きが好調になるジャンル。毎年、様々な書籍が発売されるので親子で1冊購入して、一緒に作ってみましょう。きっと良い思い出ができるにちがいありません。
寒い季節に活躍する毛糸の洋服や小物を手作りするための、編み物の本も冬になると人気が高まる書籍のひとつです。初心者向けの優しい編み物の本から上級者向けの少し手の込んだ編み方の本まで、発売されている書籍の種類も様々。型紙付きの書籍もたくさん出ているので、手軽に編み物が始められます。これらの書籍は、時期が来るとネット書店でも特集が組まれるので、売上が上位にランクインする人気の書籍。
近くに書店がないので、本を読むことがあまりない、という人が、クリスマスやお正月が近付くと、パーティーや年賀状作成に役立つ本を購入したい、と通販を利用します。こうした理由から、お正月やクリスマスに役立つ実用書が、冬に人気の書籍となるのです。



書店にはその季節に合った品物が並んでいます。冬であれば冬にぴったりの本が目立つように置かれているでしょう。文房具を扱う書店も多くあり、手紙やカードを書くことが多い冬に文房具を書店で購入する方も多くいます。冬らしい文房具を取り揃えるところもあり、書店の冬支度も多種多様です。そこで、冬におすすめの書籍や文房具など、冬の書店情報をご紹介致します。
冬におすすめの本

冬を題材にした本は数多くありますが、「手袋を買いに」と「雪の女王」が近年注目を浴びています。
手袋を買いに
愛知県半田市出身の児童文学作家、新美南吉の代表作です。狐が人間に会うとひどい目に遭ってしまうことを分かっていながら、冷え切った我が子の手を人間の手に変えて手袋を買いに行かせる母狐とその子狐、帽子屋の主人を通じて愛情や人間の心を問いかける作品となっています。冬の子供の読み聞かせの絵本の代表作として長く愛されている作品です。
雪の女王
2014年(平成26年)に日本で公開となり、大ヒットを記録したディズニーの映画「アナと雪の女王」の原作が、ハンス・クリスチャン・アンデルセンによる「雪の女王」です。アンデルセンは人魚姫などの童話も書いており、その作品は日本でも親しまれています。「アナと雪の女王」とは少し趣の異なった作品となっており、人の心の善悪を考えさせられる作品となっています。
筆ペンと万年筆
冬は年賀状や挨拶状、クリスマスカードなど手紙やカードを書く機会が多くなります。なかでも便利な物が筆ペンと万年筆です。書店でも販売しているところがありますので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
筆ペン
かつては硯に墨をすって、筆で字を書いていましたが、現在では筆ペンを使うようになりました。特に冠婚葬祭では欠かせない道具となっています。サインペンやボールペンなどの便利な筆記用具が普及していますが、熨斗(のし)袋のようにできれば、墨と筆で文字を書きたいという場面があります。そのようなときに便利なのが筆ペンです。筆ペンはいくつも種類がありますが、使い分けで重要なことは、墨の色です。結婚式などのご祝儀には濃く黒い色のタイプを使い、香典などについては薄墨を使うことです。筆のような書き心地の物や、サインペンのような物、カラーインクのタイプなど様々な物も発売されています。社会人の基本的な道具として、筆ペンや万年筆のバリエーションを揃えおくと便利です。
万年筆
日本では1884年(明治17年)に初めて横浜のバンダイン商会がアメリカ製の万年筆を輸入し、丸善にて販売して以来、愛用されてきた筆記用具です。ボールペンの普及とともにあまり使われなくなった万年筆ですが、近年また人気が出てきており若い人にも親しみやすいデザインも登場しています。その人気の理由は使う人によってペン先の角度が異なるために味のある文字が書けることです。また、万年筆のブルーブラックのインクはインクの成分が変化して時間が経つと色が変わることから公文書に使われていました。
日本各地の書店
冬は年末年始の挨拶回りや帰省で電車や飛行機などの移動手段を多く使うことがあります。長い待ち時間があるときには駅や空港にある書店が便利です。
駅や空港の書店
電車や飛行機を待っている間のひまつぶしや、移動中の読み物が欲しいときに駅や空港にある書店がとても便利です。ビジネスマンの利用が多い大都市の駅にはビジネス書や新書が揃っており、空港には洋書が並ぶなど、その店舗ごとの品揃えに特色があります。特に成田空港の第一ターミナルにある書店は洋書の品揃えがとても豊富なことで有名です。
日本最北端の書店、「クラーク書店」
2016年(平成28年)に北海道新幹線が開通し、観光客の増加が見込まれている北海道には日本の最北端に、クラーク書店という書店があります。1984年(昭和59年)に創業し、地元で愛されている書店です。場所が北海道の最北端である稚内市の中でも最北端に位置しているため、冬には最高気温が氷点下前後の日が続き、ときには吹雪くこともあります。日本最北端の本屋さんは、北海道の歴史や文化について分かる本の他、「ひぐま」に関する本もずらり。レシピ本からベストセラー小説まで品揃えが豊富です。日本最北端の稚内市に訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみて下さい。
冬の書店は、手帳、カレンダー、年賀状など生活やビジネスに関するアイテムが一斉に出揃うため、売場が多くの人で賑わいます。最新のトレンドやこれからの流行を見付けるためにも、冬の書店は要チェックです。
手帳
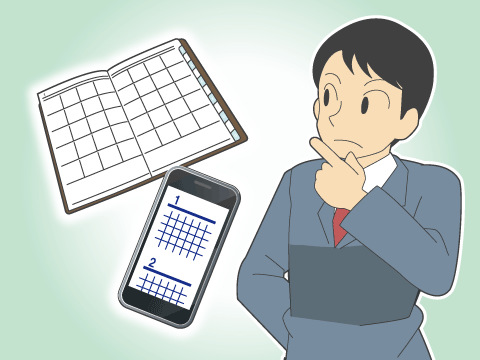
年末が近づくと、ビジネスマンやOLを中心に売れ行きを伸ばすのが手帳。多くの書店では特設コーナーを設けることから、年末年始にかけて最も需要が見込まれる商品のひとつと言えます。スマートフォンやタブレット型端末などの電子機器のスケジュールアプリを利用する人もいますが、ブックレット型のシステム手帳などの愛好者はまだまだ大勢います。毎年新しい手帳を買い換えることが楽しみにしている人もおり、幅広い年齢層で根強い人気があります。
手帳は、仕事やプライベートのスケジュール管理に主に用いられ、自分の予定が一目で分かるのが大きなメリットです。その他にも気がついたことや忘れていけないことを、いつでも手軽にメモできるのも人気の秘密。女性では色違いの文字で公私の予定を使い分けたり、家族や友だちの誕生日を記入したりと、独自の利用法で楽しんでいます。こうした機能性や利便性を高めるために、システム手帳では地図や鉄道の路線図が印刷されていたり、文具や名刺などを収納できたりと、多彩なリファイルも販売されています。リファイルをいろいろ組み合わせて活用することで、自分の使いやすい手帳にアレンジできるわけです。また、システム手帳はバインダー式なので、使い慣れたカバーはそのままで、手帳部分を変えたり追加したりすることもできます。
新しい1年も、まっさらな手帳が充実した内容で埋まるようにしたいですね。
カレンダー
11月に入ると、新年のカレンダーが書店で販売されます。壁掛けから卓上まで用途に合わせた様々な物が並び、店内を訪れたお客さんも足を止めて、最適な物を選びます。写真やイラストを全面的にあしらった物や、スケジュールを記入できる余白入りの物、他にも格言や名言を毎日紹介する日めくりカレンダーなど、毎年多彩なカレンダーが登場。商店や取引先からもらえるカレンダーを利用する人も少なくありませんが、書店などで販売されているカレンダーは、芸術的な物やユーモアのある物など、見る人の心を引きつけます。
カレンダーは生活の中でとても重要で、仕事や家族のスケジュールを考えたり、暮らしの計画を立てる上でとても役に立ちます。二十四節気や六曜が記入してあると、行事や冠婚葬祭に便利。新しいカレンダーをめくって、「連休が何日ある」「誕生日は何曜日」など来年の予定に思いを巡らすのも悪くありません。
最近は、月曜日を週の頭にして、ビジネスとしての使いやすさを求めたカレンダーもあり、機能的にも充実しています。
年賀状
毎年11月下旬に郵便局で年賀ハガキが発売されますが、手作りをしているヒマがない人や、メッセージ性を強調したい人向けに印刷された年賀状も書店の店頭に並びます。その年の干支を描いた物からお正月にふさわしい絵柄を施した物まで、多種多様の年賀状が店頭を賑わせます。
最近は、電子メールやSNSなどが普及して、簡単に新年の挨拶をすませる人が多いようですが、「普段はなかなかお目にかかれなくても、年賀状くらいは出しておこう」と考える人も多く、中高年を中心に確かな人気を誇っています。パソコンやプリンターが普及して、誰もが簡単に年賀状作りができるようになりましたが、市販の年賀状はそれなりにクオリティが高く、相手によって絵柄を変えることもできるメリットがあります。また、私製ハガキでも年賀切手が発売されるので、元日に新年の挨拶を届けることができることから自分好みの絵柄を選んで、大切な人に年始の挨拶状を送りましょう。
また、喪に服している人は、喪中欠礼のハガキをできるだけ早く送り、年賀状が不要なことを相手に伝えます。書店では、年賀状とともに喪中欠礼のハガキや寒中見舞いなども販売されていますので、忘れずに出すようにしましょう。
ウィンターシーズンの書店では、クリスマスから新年にかけてのアイテムが目立ちます。クリスマスカードから新年の運勢を占う本まで、年末年始の行事に関連したものが売場を彩ります。
クリスマスカードを贈ろう
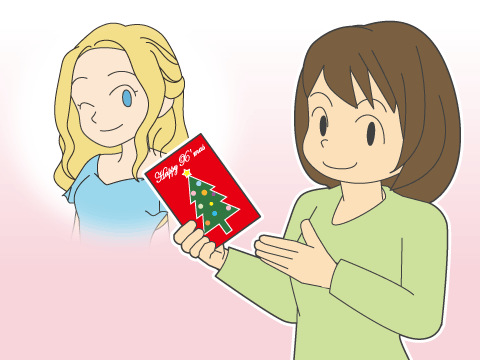
欧米では、クリスマスにメッセージを添えてクリスマスカードを贈り合う習慣があります。日本ではクリスマスがすっかり定着していますが、カードを交換し合う習慣はあまり浸透していないようです。それでも、少し大きな書店では、グリーティングカードのコーナーがあり、そこにクリスマスカードを見付けることができます。クリスマスリースやサンタクロースのイラストが描かれたものや、英文のメッセージを強調したものまで様々な種類があり、購入する人は、外国人や海外に友人を持つ日本人などが多いようです。クリスマスカードの売場には特別にディスプレイされることも多く、年の瀬が近いことを告げています。贈る時期としては12月中旬からクリスマス・イブまでで、それぞれ思い思いのメッセージやお祝いの言葉をカードに書き込みます。
日本のクリスマスカードには、「Happy X'mas」などクリスマスを祝う言葉だけが添えられますが、欧米では新年を迎える言葉も一緒に書き添えることが多いようです。日本では年賀状があるため、新年の挨拶とクリスマスのお祝いは切り離して考えているのでしょう。
最近は年賀状も電子メールでやりとりすることが多くなっていますが、クリスマスくらいはカードに手書きのメッセージをしたためて贈ってみてはいかがでしょうか。
クリスマスプレゼントに図書カードを
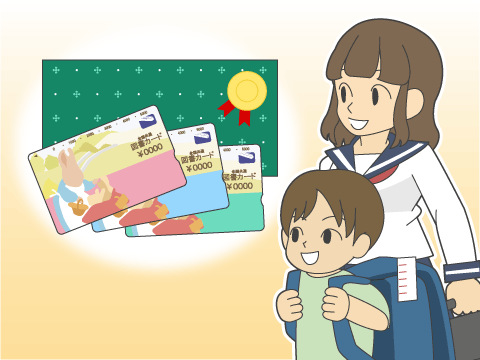
クリスマスプレゼントに何を贈って良いのか分からない場合は、図書カードを贈りましょう。いつでも持ち歩けますし、好きな本をすぐ購入できます。特に児童や学生などへのプレゼントには最適です。
図書カードは、それまで流通していた図書券から引き継いで1990年12月から発行が開始されました。従来の図書券は、書店側にとって釣り銭の処理が面倒でしたが、図書カードはプリペイド式なので、専用端末機に通すだけで支払いが完了します。上部に残額の目安となる数字が印刷されており、使用するとテレホンカードのようにパンチ穴が開けられます。額面は500円から1万円までの6種類が用意されており、図柄は様々です。オリジナル図書カードを製作することも可能です。封筒に図書カードとメッセージを入れれば、ステキなプレゼントになります。
なお、従来の図書券も販売は終了していますが、現在も各書店で使用することができます。
新年を占う
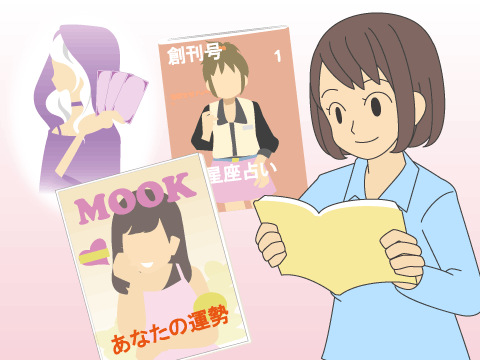
年末に書店で多く並ぶのが、新年の運勢などを占う様々な本です。占星術から東洋易学までありとあるゆる占いの本が平積みにされます。誰もが「来年こそ良い年に」と願っており、これらの占い本を見ては、行動を決めたり、ラッキーアイテムを探したりする人も多いようです。
占いは古代から世界中で行なわれており、古代ギリシャや古代ローマには占いを職業とする占星術師がいた程です。西洋では主に占星術が信仰され、東洋では中国の陰陽道が信じられてきました。首領や国王の中には、占いを以て国を治める手がかりにした時代もあり、それは天の声や神の声と同じように崇拝されていました。日本でも来年の豊作を占ったりする祭りや行事が全国各地にあります。科学が発達した現代では、占いを100%信じたり頼ったりすることはありませんが、多くの人が心のより所にしているのは事実です。仕事や生活が高度化し、人との結び付きが複雑になる程、悩みやストレス、不安も多くなるため、占いに安堵感や方向性を求める人も少なくないようです。
それでもあまり重く捉えず、会話の話題として手に取るほうが読みやすいでしょう。来年の運勢が気になる人も、そうでない人も何か生活のヒントが見つかるかも知れません。









